 うつしき
うつしき
 うつしき
うつしき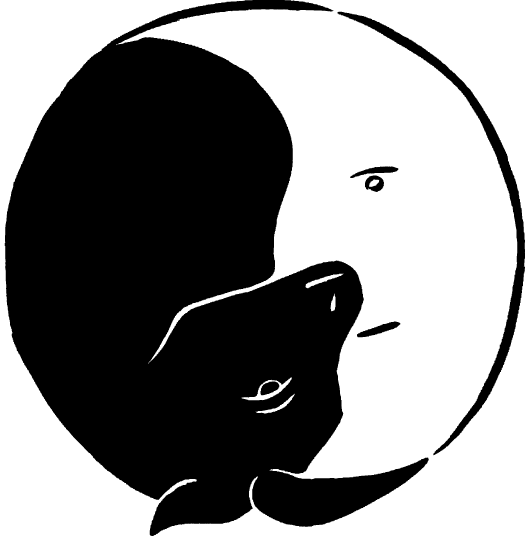

真夏に開催致しました、清水志郎展。
120パーセント自身の手で掘られた土によって成り立つ作品群。
今展では野焼き作品も多く、うつしきに原始の風と、人類の始まりの頃のような気配が漂いました。
土を、焼く。シンプルな行為に見える陶芸が、これほどまでに掛け合わせ多様で面白いものなのだと気づかせてくれました。
志郎さんの作品は、そこにポンと在るだけで、空間と時間を奥深くまろやかにしてくれる。
立秋を過ぎた晩夏の頃、身近にある山や庭先の土に想いを馳せながら、対話の模様をご覧ください。

―さて、今展は野焼き作品がメインでの展開となりましたが、どうしてでしょうか。
清水:小野さん(うつしきオーナー)から、“水を掬うもの”というテーマを頂いて。それで、人類が水を手以外でもっと掬いたいと思ったときに作られた器、みたいなものを作りたかったんです。そうすると、焼成方法は野焼きしかないなと。当時は窯もなかったやろうし。
―元々、野焼き作品を多く作られていると思うのですが、野焼きしたくなる理由を教えてください。
清水:野焼きだからというか…単純に、“土を焼く”ということに興味を持っているので電気窯でも登り窯でも穴窯でも焼きますし、そのうちの選択肢のひとつという感覚です。
何故こんなに楽しんでいるのか・・・分からないですけど、多分、あまりやったことがないからだと思いますね。
―野焼きを始める陶芸家が増えているようにも思います。時代の流れなのでしょうか?
清水:時代が求めているっていうような、大それたことを言えなくもないですけどね。時代感覚を肌で感じて、キャッチしているんだと思います。そういうこと、あんまり言いたくはないんですけど。科学が進めば進むほど、IT化すればするほど、真逆の原始的なものを人間が欲しているような感じ。「そもそも、どうやってたんやっけ?」ということを考えさせられるようになってきている時代というか。

ー志郎さんがはじめて野焼きをしたのはいつ頃ですか。
清水:ちょうど、土堀りを始めた30歳前後から野焼きもやっていました。当時は、温度を上げすぎて爆発するとかもありながら。今回は温度を上げすぎないことを狙って、土を塗って蓋をした空間の中に作品と薪をいれて、空気が入らないように。ただ序盤、空気が通らなさ過ぎて、あまりに温度が上がらず困ったんですけど(笑)
―うつしきの取材動画で拝見して驚いたのですが、野焼きといってもまるで小さな窯のような形状でされていたんですよね。
清水:そもそも野焼きの仕方って沢山あるというか、こうじゃないといけないというのは無いので、やってみて試行錯誤するしかなくて。今回は窯寄りのやり方でしたが、「上にあがる熱をなんとかしたい。焼きたいものは下にあるのに!」みたいな気持ちから。みすみす放熱してもったいないやん、というような。前回は屋根もない状態をやっていて、色々な段階を体験したい気持ちがあります。

―野焼きや土堀りを始めたのは「行き詰っていた」という30歳の頃と伺いましたが、当時どういう行き詰まりを?
清水:そういう家(代々陶芸家)に生まれているからなのか、他にやりたいことが無かったからなのか分からないですけど、辞めたいという選択肢は持っていなくて。ただ、辞めたいとは思わないけど、どうしていけばいいかも分からない。果たして自分に才能があるかどうかも分からない。というように、自信を無くしていっていた頃です。
―それで、土を掘り始めて。作陶に影響はあったのでしょうか?
清水:すごいありましたねぇ。土堀りに全て救われたような、そういう大きな転機やったというか。
―そんなに!
清水:最初に掘りに行ったのが、手を加えずともすぐに使えるような土で。「掘ってすぐ使えるやん」と感動しつつ、焼いてみないと分からないのでとにかく焼いてみて。焼いてみると色々発見があり、そうなると、周辺の土は?他の土はどうなんやろう?焼き方も色々あるし、同じ土でも焼き方を変えるとどうなるん?と考えるようになって。それがまあ、とにかく楽しかった。

―そういう感覚は、それ以前は湧いてこなかったのですか?
清水:いや、一応あるんですよ。でも、何かを生かそうとしてというよりも、自分のやりたいことや目的が先にあって、そこに合わせてああやってみようこうやってみようというアプローチなんです。でも土を掘ってくる場合は、あくまで土ありきで、この土だったらどうなるかな?こう焼いてみようかな?という。全然ベクトルが違うんですよね。それが面白かったし、自分に合っていました。
―成り行きや出会いに身を任せる、みたいな。
清水:そうそう。思えば時代的にも、“個性、個性”言われるのがだんだん陰っていた時で。
僕もそれまで、なにか個性的なものを作らなければならないと強迫観念のようなものにずっと駆られていたんです。でも、土を掘ってきてそれをどうにかしようとしていると、決して個性を出そうとしているわけではないにも関わらず、個性が“出てきてしまっている”という状態になって。

―特に、志郎さんは“産地ではない場所の土”を掘って使っていますよね。
清水:産地で掘ることと、産地でない場所で掘ることはとても意味が違って。産地で土を掘るのは当たり前といえば当たり前。産地は、粘土がすごく沢山の量とれるものですが、そうでないところは、そうではない。沢山粘土があるわけでもないところを自分で探し当てて、カリカリと掘っていく。「その辺にある土をなんとか生かしてやろう」という精神がないとできないように思いますね。
—その精神、取材動画で垣間見ました。使いにくそうな粘土を前に「使えない土はないと豪語したいから」と言って手を加える様子が非常に印象的で。
清水:なんとかしたいですねぇ。基本、土を単味で使っているのでそういうことが起きるんです。土を使いやすくしようと思えば、他の特徴を持つ土と混ぜることでそうできるんですが、そうするとその土の持ち味が半減してしまう。特徴を知るためにも、掴むためにも、生かすためにも、混ぜないでやりたいんですよ。水漏れについても、させたくないと思えば他の土を混ぜたらいいんですが、その土の本来が見えなくなってしまいます。

―今回うつしきでも一部の作品において値段をつけずにオークション(入札)形式による販売を試みましたが、オークションを始めたきっかけが気になります。
清水:5年ほど前から展示会時に、キズがあるから完品としては並べられないけど焼けは良いようなものを一応持って行って値段をつけず棚下に置いていたら、「これいいやん」とお客さんが目をつけてくれはることが増えて。「傷あるし水も漏れるし割れてるから値段が付けられないので、値段をつけて下さい」と言ってお客さんに値段をつけてもらって持ち帰ってもらう流れが生まれました。
―へぇ。
清水:そういう現象が起きてだんだん面白くなっていた頃、ある展示会で2人展をしたときに、もうひとりの陶芸家と共作した作品ばかり出した時があって。どっちの作品ともいえないようなものに対して、値段どうする?って、ほんまに値付けが分からないのでオークション制を取り入れてみたんです。その時のお客さんの反応、値段の付け方、それを見た自分のギャップ、真剣勝負な感じ…面白いと感じて。

―難しいこともあるように感じるのですが
清水:でも、教えてもらうことの方が多い気がしますね。自分では良いと思っていたものがそうでもなかったり、逆もしかり。お客さんそれぞれの考え方や価値観が垣間見えることも。それに、結局売り上げという面ではプラスマイナスゼロくらいに着地します。案外すごく売り上げが落ちるわけでも、上がるわけでもないという。
―ありがとうございます。最後に、これから志郎さんが作ってみたいものや興味の方向はありますか?
清水:逆になんかありますか?(笑)こういう展示会見たいとか。
―(笑)。好き勝手言わせて頂くと、大きなもの、見たいです!椅子とか家具とか。大きさの制約を取っ払ったスケールで。志郎さんの作品は器としての機能や用途以前に、その土がそのままありありと生かされ存在するような魅力があるのでそれを生かせるような。
清水:意外な角度からきたなぁ。窯のサイズに縛られてしまうところがあるんですが、確かに野焼きなら大きさの制約は外せるかも分かりませんね。
―ありがとうございました!
清水:ありがとうございます。
今回の対話を終えて
昨年、住まいも作業場も完全に京都から滋賀に移った志郎さん。
かつておじい様が使っていたという作業場には、おじい様が残した作りかけの作品や掘っていて残った土など、沢山の痕跡があると言います。
自身の身体でその影響を受けながら、大きな流れの中で生まれる作品は、静かな確かさがあるように感じます。
話を聞いていると、果たして志郎さんは何か作っているのか?
土をサポートしているようにも見えるその姿がこれからも気になって仕方ありません。
聞き手・文 : のせるみ
[ 対 話 – 清水志郎 – (2020) ]
清水志郎 展
7月23日(土) – 7月31日(日)