 うつしき
うつしき
 うつしき
うつしき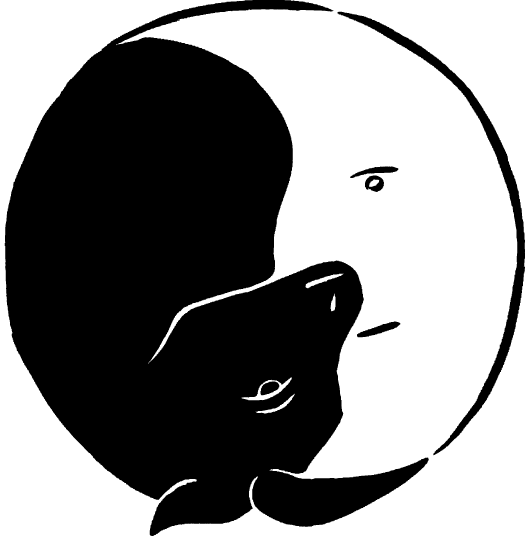

2年ぶりの開催となった、市川孝展。
熱狂的な空気に包まれて、展示初日にほとんどの土瓶や耐火皿が旅立ってしまいました。
「旅立ってしまった」なんて、作り手の作品をご紹介するギャラリーの立場で言うにはおかしい言葉ですね。
嬉しい出来事についてそう思うのは、市川さんが誰よりも楽しそうに自身が生み出したものを使っている姿を見たからかもしれません。「勢いの中で、どれだけの方にその好奇心を届けられただろうか」と。
飾りたくなるよりも、使いたくなる、市川さんの作品群。
作品を手にした先の景色が鮮明に想像できて、心底ワクワクさせられるのはどうしてでしょうか。使いたくなる形の理由は、なんなのでしょう。
市川さんの作品と出会えた方も、展示で存分にご覧いただけなかった方も、これからの出会いを楽しみにしている方も。
初夏の昼下がりお茶を片手に、ゆっくりと対話の模様をお楽しみくださいね。

―ものづくりをしたいと思いはじめたきっかけを教えてください。
市川:今、ぱっと頭に浮かんでくるのは父の手なんですね。といっても別に父は作品を作っていたわけではなく、家を直すだとか、郵便ポストをつくるだとか、なんでもない日常生活のものづくりなんですけれども。
―幼い頃からものづくりの道にまっしぐらですか?
市川:というわけでもなくて、少年時代はホッケーに打ち込んでいました。当時は競技人口が少なかったこともあって全国大会なんかにも出場して。転機は中学3年生の時、先生から美術部を作らないか?と声をかけられたことです。
―ホッケーから美術の方面へ!
市川:高校でも美術部を作り活動を続けたものの、ホッケーを続けた人が輝いて見えて、負けたくない~と思いつつ彼らの練習風景が見えるのとは反対の窓から見える伊吹山をひたすら描いていました。専門的なことを教えてくれる先生がいないことにもモヤモヤしながら。進路を決める時が来て、美大や芸大も考えましたが、デッサンの勉強を始めるには遅すぎることを知りました。結局、教育学部の美術を目指すことにして。

―共通一次試験に失敗して第一志望校を諦めなければならなくなり、二次練習のつもりで受験した家から離れた北海道の教育大学に合格したとのことですが、そこではなにを?
市川:もちろん美術をするために入ったので「中学美術」に進むつもりが、どうも頑張りすぎたことが逆効果で5教科の点数が妙に良かったらしく「市川さんは、小学校課程です」と。「えええ~」みたいな。
―えええ~。
市川:加えて、広い水平線しかない北海道の大自然を前にどう描けばいいのか、という感じで。それまでの人生、「美術=絵」しかないと思っているくらい絵しか描いてきていないのに、いざ感動している「この北海道の雄大さを描こう!」と思っても、湿原や草原がただの一本の線になってしまう。絵で雄大さを表現する技術を知らないわけです。
―平面の限界を感じた、と。
市川:きっかけとしては2回の夏休みを使って自転車で北海道一周をする旅に出た際、美術館の作品や、行く先々で様々な分野のものづくりをしている人達と会って。何やら「立体が面白いよ」ということを聞いてしまった。大自然の雄大さを絵で表せない気持ちがあったなかで「そうか、平面だけじゃないのか!」と、彫刻のほうに気持ちが向きはじめました。
―彫刻ですか。
市川:それから、頑張って彫刻をするんです。一生懸命。けれどもなにか違う。頑張っているので賞なんかに入ったりもするけど、なにか違う、みたいに思う時期が続いて。そのうちに、果たして大学を卒業してそのまま教諭になりたいのか?という葛藤も湧いて。もっと自分の彫刻を広げたいということで大学院に進みました。

―大学院はどうでしたか?
市川:…実は大学院でも、一番入りたかった研究室に入れなかったんですよ。賞を取るような真面目な、“そういう”作品を作っていたことが影響しての判断で「市川君はこっちだろう」と。本当はもっと自由な作品が作りたくて来たし、指導を受けたい先生がいたんだけども。再び「えええ~」という感じ。
―まっすぐ真面目にやることが、思わぬ方向に繋がるなんて。
市川:かつてのホッケーじゃないですけど、入れなかった研究室に入った人をライバルだと勝手に思って、横目で見ながら頑張ろうとやっていました。でもある日、東京芸大の彫刻の先生が学生の作品を見に来てくれはった時、僕の作品を見た後に「うーん、よくないなぁ。唯一いいのは、背中だけ、だなぁ。」と言われて。ライバルだと思っている人は褒められて。
―ああ…。
市川:唯一いいと言われたのは、背中だけ。人間の彫刻だったのですが、時間をかけられずに、作りこめなかったのが背中で。極めつけに、「市川さんの作品には、窓がない。」と。
―窓、ですか?
市川:人間の形を作っているのに、窓ってなんや!なんて思いつつ、当時はそれからスランプに陥って。今となっては、だんだんその意味が分かってきています。作品だけで完結せずに、見る人の想像を掻き立てるような、受け手の感覚が乗って返ってくるようなことだったのだろうと。一方方向に、かっこいいでしょ綺麗でしょというだけではつまらないし、魅力が弱い。

―それから、陶芸に辿り着くまでの道のりはどのようなものでしょうか?
市川:院修了後に、母校の高校の臨時講師に就いたのですが、「自分はここではやっていけないだろう」と感じて。何であれもの作りができるところに行きたいということで、様々な美術関係の仕事を探しまわり、面接を受けては落ち、その中でご縁を頂いたのが信楽焼の作陶所でした。
―偶然の成り行きともいえますね。
市川:沢山の学びやご縁を頂きながらも、勤めて3年たつ頃「自分は進みたい方向に進んでいるのか?」と再び自問し始めて、一度独立をしました。ちょうどバブルのころでした。その後、独立して準備した環境を離れなければならなくなり、改めて全国の気になる陶芸家の方に話を聞き歩くうちに出会った作家さんの下で、再度弟子としてつかせて頂いて。
―そこでの経験はいかがでしたか?
市川:それまで陶芸家というのは「先生」という感じで思っていたところがあったんですが、そこは全くそんな空気ではなく静かで穏やかで、でも焼き物には熱いところで。自然の中で遊ぶことだとか、生活の中で楽しむことだとか、とにかく豊かな営みをされていました。自分の中で別々だった作陶と暮らしと遊びが、実は絡んでいる、というふうに気付くことにも繋がって。
―作陶と暮らしと遊びが絡んでいる、というと。
市川:作品を作るための作陶、生活するための暮らし、息抜きの遊び、という分けられたものではないんやと。作品は生活のための道具であったり、遊ぶための道具であったり。反対に、暮らしや遊びの中から、こういう形はどうだろうか?と思い浮かぶことがあるわけですから。それ以前とは、ものづくりに対しての在りようみたいなものが違うというか。

―市川さんはご自身の作品を「器」ではなく「道具」と表しますが、どうしてでしょうか?
市川:器となると、完結している場合がある感じがあって。それそのものが完璧というような。でも「道具」は、使い手がいて存在する。ものだけで完結するのでなく、使いだしてようやく感じてもらえるもの。だから、売りたいよりも感じてほしいという想いのほうが強くなっています。
―作品自体を売っているわけではないように聞こえます。
市川:あくまでも、道具を手に取ってくれる人が暮らしの風景や楽しい何かを想像できることをしたいというか。道具の先の、その先の景色や時間を用意するような感じで。それぞれの道具使いの先に、それぞれが好きな形、色が生まれてくるんじゃないかと思っているので。そうやって欠けたり垢や染みがついたりしてその人の歴史や暮らしのリズムが残ると、その人にとっての器が完成していく。
―「経年変化かっこいいでしょ」みたいなことよりも、もっと楽しそうな感じですね。
市川:道具のその先を委ねる感じ…。楽しいことを用意して。もっというとそのときは、器の存在はなくてもよくて。なんか楽しいよねと思ってやっていることの道具が、ふと気が付いたときに「ああそうか、これ市川の作品やったか」みたいな。

―市川さんの道具性を感じさせる代名詞として、今展でも人気のあった耐火皿があるように思うのですが。
市川:もともと耐火皿は、耐火皿をつくろうとして作ったというよりも、古道具屋で出会った古い石皿にイメージをもらって形になったんです。
―古い石皿?
市川:石皿の裏側が真っ黒やったんですよ。ああかっこいいな、こんな仕事したいなと思いながら、しかし何故黒いんだろうか?と思って。もしかして、台所で鍋のように使っていたんだろうか、もしそうだとしたら面白いなぁという具合に、イメージが湧いてきて。火にかけられる道具を作りたいと。
―わくわくします!
市川:そうこうして、石皿を買った古道具屋に出来上がった耐火皿を持っていくと、偶然お客さんとして居合わせた料理家の方が、その場でちょっと使ってみましょうと。使い道は焼肉か鍋か…しか想像していなかったところに、パンやソーセージやトマトやアスパラガスなんかを焼いた温かな朝食が出来上がったんです。その行為が、とても斬新なものとして自分の中に入ってきて。そこから料理と道具(器)という組み合わせの展示会を多くしていくことになります。「これ、こうしたら美味しいよね」という会話が飛び交って、だれも器のことは話してないような展示会(笑)

―料理と道具(器)という話がありましたが、近年の市川さんは「お茶を嗜む作家」として紹介されることも多いですよね。
市川:嗜むというより、遊んでいる感覚です。もともと日本の茶道は少しやっていたんですが、今に至るのは台湾茶・中国茶の自由さや豊かさに出会ってしまって以降のことです。
―台湾茶、中国茶との出会いはどのようなものだったのでしょうか。
市川:耐火皿に続いて火にかけられるものということで土瓶を作り始めたころ、当時台湾に住まわれていたお茶の先生が土瓶を気に入ってくださって。もういくつか欲しいと言って下さったけれども、ご注文をお受けして全く同じものを作るというのはできなかったので、「台湾で個展をさせてください」と申し出て。下見で台湾に行くと、いろんな台湾茶を教えて下さって。
―お茶三昧!
市川:その先生のお弟子さんたちも各々が持ち前の茶器を使って、設えや雰囲気は人によって全然違うけどそれぞれ美しくて、中には自分で焙煎する人もいて、どのお茶も個性があって美味しい。「なんて自由なんだ!」と衝撃的でした。とにかくみんな楽しそうにやってるんです。

―まんまと台湾茶、中国茶にはまっていくわけですね。
市川:現地で教えてもらったお茶を日本に帰って振舞っていると、「市川、これの方が美味しいぞ」「もっと美味しいお茶があるぞ」という具合に、次から次へとお茶を教えてくれる流れが出来上がって。どんどんお茶遊びが自分のなかで盛り上がっていく。そうすると、どうしても原産地や古樹の存在が気になりはじめてしまって。
―はい。
市川:行ってみたいと言い続けていると、西双版納(シーサーパンナ)というかなり山奥のお茶の原産地に行ける機会を得たんです。どれがお茶なんだろう?なんて思っていると、指さされたのは見上げるような大きな木。木登りしてお茶の葉をとるような、樹木でした。
―お茶が樹木!?想像できません。
市川:お茶、お茶、と思っていたけれど、お茶は樹木の葉だということを目の当たりにして。そのころから、自分がやっていることは“植物と火と水のこと”なんじゃないかと思い始めて。そうすると、スープとお茶の境目もなくなってくる。

―スープとお茶の境目がなくなる??
市川:料理云々、お茶云々を通り越して、そうか全ては植物か、水か、火か!という。陶芸もそうです。あれこれとカテゴリーを分けて表現しなくても、根っこのところで繋がっているんやと。身の回りのほとんどのことが、植物と火と水で出来上がっているように見えてきます。自分の中では今、“煮茶”まできていて、花や葉っぱやいろんなものを煮て遊んでいます。根菜類を煮ればスープで、葉っぱを煮たらお茶?分からないでしょう。(笑)
―市川さんは陶芸やお茶という別々のことではなく、サービスでもなく、“植物と火と水”の出会いから生まれる表情を遊ぶというところで共通のことをしているんですね。
市川:そうやると、楽しくて仕方ない。だから作品を手に取ってくれる人にも、遊びたい!とか楽しい!という感覚で出会ってもらえるようにしたい。ブランド品みたいな感覚ではなく、ひとつひとつの出会いを豊かに味わうような気分で。その為には、自分自身も作品を全部もっと存分に楽しんで、感じ取る時間を増やしていきたいと思っています。その結果、器や道具がお金になって「応援してもらえる」という風になると、嬉しいなと思います。
―ありがとうございました。
市川:ありがとうございました。
今回の対話を終えて
どんな靄や霞の中も、驚きと発見、好奇心と楽しさを方位磁針に進んでいるように見える市川さん。
なんでもない生活まわりのものを作っていたお父様にだんだん似てきたというその両手は、これからも”植物と火と水”と遊ぶ世界に私たちを誘ってくれることでしょう。
次なる遊びはなんなのか、気になって仕方がありません!
聞き手・文 : のせるみ
[ 対 話 – 市川 孝 – (2020) ]
市川孝 空想民族 展
4月29日(土) – 5月8日(日)