 うつしき
うつしき
 うつしき
うつしき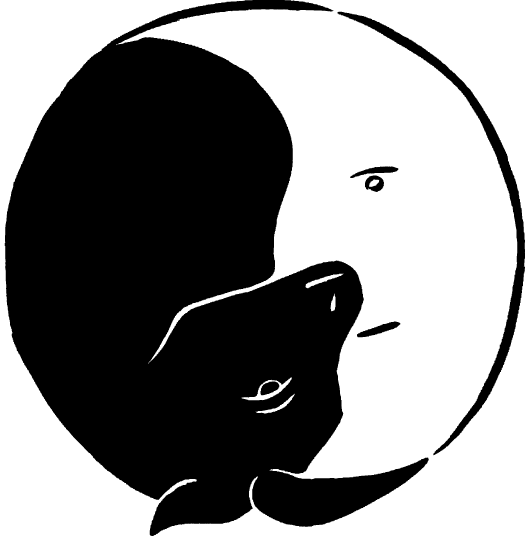

よい焼き物をつくりたい、そのために繰り返される無数の検証。
「銀彩の作品は、通常の4倍くらいの時間がかかります」。
効率化に囚われすぐに結果だけを求める時の流れの中、どうして失敗を恐れずに毎回挑戦し続けることができるのだろうか。
そこには、純真で尽きない探究心とオリジナルを追求し続ける姿勢がありました。
これまでの軌跡を辿ったインタビュー前編に続き、後編では制作過程についてのお話です。
 iPhoneの指紋認証が反応しなくなるほど繰り返す、うつわの底や表面を削って整える工程。
iPhoneの指紋認証が反応しなくなるほど繰り返す、うつわの底や表面を削って整える工程。
銀彩の作品ができるまで、容易なことではありません。色ひとつとっても、釉薬に調合する成分の割合や、焼く温度によって色の出方は異なります。土の産地や焼成温度、窯入れの密度や場所など、気を遣うべき点は無限に増えていきます。
福村さんは、何百回にも及ぶ釉薬のテストを行い、どんな材料をどれくらいの割合で混ぜ合わせ、何度で焼くと色の交わりが生まれるのか試行錯誤を重ねてきました。たくさんの手間と時間をかけて、銀彩の作品が生み出されています。
「白釉をかけた上に気泡の出るマンガン系の釉をかけるので、焼き上がった時は表面がボコボコしています。それを一つずつグライダーで削り、さらにペーパーで滑らかになるまで磨きます。その上から銀の釉薬を塗って、また焼きます」。
 完成まで気を抜かず、温度の上がり具合を30分毎にメモを取り窯焚きを行う。
完成まで気を抜かず、温度の上がり具合を30分毎にメモを取り窯焚きを行う。
数日以上かかることもある作業工程。効率のよさではなく唯一無二であることを重視し、再現性を求めないことは、生み出したものがいつまでも特別な存在であり続けることでもあります。
「細やかな作業もあるのですが、手間を惜しまずに、丁寧にやっていくだけです」という福村さんは、自分がものづくりをする意味を常に問い続けている。
「銀彩の器は、ある程度世の中にだし尽くされていると思うんですけど、自分がイメージする銀彩の一歩次を表現したいと思っています。様々な釉薬との組み合わせだったり、まだ人がしてないようなチャレンジをしていていきたいです」。
 お花の稽古を習い始め、形だけでなくお花を生けるシーンなど、使い手の気持ちを鮮明に思い描きながら制作と向き合う。
お花の稽古を習い始め、形だけでなくお花を生けるシーンなど、使い手の気持ちを鮮明に思い描きながら制作と向き合う。
頭に浮かんだ形は図面にするのではなく、ろくろを回して自然とでき上がる形を大切にしている福村さん。
「漫画が好きで、特に井上雄彦さんの作品を読んでいます。『スラムダンク』の流川楓が両目を瞑って『体の感覚を…信じろ』とフリースローをシュートするシーンがあるのですが、ろくろを回している時はその感覚に近い状態だと思っています」。
決まった型のようなものはなく、成形に入ると手を動かしながら着地点を探す。正解のないものづくりの中、黙々と作り続けることで必要としてくれる人と巡り会う。そういう人の中には、プロの料理人もいます。海外や日本の新進気鋭の飲食店のシェフ達から、「作品を使わせて欲しい」と言われる機会も増えたといいます。
「もっと派手なテクスチャーで自己主張をしていた時期もありましたが、そこを一歩引いて、どうやって料理が映えるように静かに表現できるか。要望に耳を傾け、最適な表現方法を模索しながら、料理のキャンバスになることを心がけるようになりました。自分の想像を超える盛り付けをしてもらったのを見ると、わくわくします」。
 作品の構想は、陶芸以外のものからインスピレーションをもらうことが多いと話す福村さん。骨董品収集や縄文式土器や弥生式土器、須恵器からスリップウェアまで、時間があれば手にして眺めているという。
作品の構想は、陶芸以外のものからインスピレーションをもらうことが多いと話す福村さん。骨董品収集や縄文式土器や弥生式土器、須恵器からスリップウェアまで、時間があれば手にして眺めているという。
福村さんが生み出す銀彩や金彩は、複雑なテキスチャーをもち、そのお皿の表情から星空や山脈を連想する方もいます。心の片隅に残り、何度も違う角度から見て、また手にしたいなと想いこれがれてしまうような。
「うつわの中に、特定の表情を描こうというのはないです。でもそれが偶然につながって見えるっていうのはすごいあると思います。ただ、作品に対してこれはこういうモノと言葉であまり決めたつけたくないんです。受け取り手がその時の感覚や感性を大事にして、楽しんでもらえたら嬉しいです」。


制作で行き詰まった時には初心を忘れないようにと手にして、その頃の気持ちを思い出すという。
訪れた工房には、これまで制作されてきた作品が置かれていました。形や大きさ、使われている釉薬もさまさまざまで、福村さんのこれまでのものづくりの変遷を物語るよう。
今回の取材では、いままで作陶した中で思い入れのある作品を持ってきてもらいました。大学卒業後、「日月窯」に戻り薪窯で焼いた花瓶の作品。どうしてこの作品を選んだのだろうか。
「技術や知識はこの時期より今の方があるのですが、この表情は狙っては作れないです。この作品は、責め焚きの時に薪を入れすぎて棚板が全部崩れちゃったんですよね。その時に作業工程も終盤だったので、そのまま倒れた上から薪をがんがん投げてできあがりました。本来は白い花瓶をイメージしていたのですが、偶然な質感を生んだことに対して自分の中で衝撃で。その時にいろんな組み合わせというか、焼き方も本当に自分にあったスタイルで良いんだなというのを感じましたね。それから薪窯で焼くときも自由にチャレンジしながら、失敗を繰り返して焼いています」。
「話すのはあまり得意じゃないんです」と撮影中リテイクを繰り返しながらも、真っ直ぐな姿勢で一つ一つの質問に答えてくれた福村さん。数年前から愛用し続けている黒いツナギは作陶中のユニフォーム。
2月20日より開催した『陶芸家 福村龍太 展』。銀彩から薪窯で制作されたカップやうつわが数百点程並び、日にちが経つにつれ、たくさんの作品が旅立っていきました。
金属の釉薬だけでなく、土の質感を活かしたものと、両方の作品を作っている福村さん。そこにはひとつの作風にとどまらず、常に新しいことに挑戦したいという想いがあるからです。
「銀彩は低温で焼くので、使うのは電気とガス窯で、比較的、熱のコントロールがしやすいんです。今後は薪窯でしかできない、灰をかけた作品を増やしていきたいと思っています。ろくろ、釉薬や窯の状態まで、細心の注意を払って作っても、そこに偶然の美しさが入り込む余地があるのが、薪窯のおもしろい所です」。
 作陶中、スピーカーからはお気に入りのヒップホップ音楽をかけることも。展示前に訪れた時期は『THA BLUE HERB』の“TRAINING DAYS”をリピートして聴いていたといいます。
作陶中、スピーカーからはお気に入りのヒップホップ音楽をかけることも。展示前に訪れた時期は『THA BLUE HERB』の“TRAINING DAYS”をリピートして聴いていたといいます。
今回の展示は、オープン前から列ができるほどたくさんの方々から注目を浴びていました。福村さん自身、いまの現状をどのように受け止めているのだろうか。
「正直、時代の流れやカテゴライズなどはあまり意識していなくて、自分がどういう姿勢で作品と向き合っていくか。常に新しいものを作りたいという気持ちがあるので、好奇心が赴くままにこれからも制作には取り組んでいきます。いまは明確に何を作りたいっていうのは正直そんなにないんですけど、常に作っているものから少しずつ自分の中で変化は求めています。失敗を繰り返しながらも挑戦して、それが5年後10年後どういう風になってるのか。自分自身が一番楽しみでもあります」。
今回の対話を終えて真っ直ぐな姿勢は人の心に突き刺さる。展示期間中に、福村さんは追加で100点以上の作品を持ってきて、うつしきの空間は日々違った景色が広がっていました。その熱量は作品を通じてお客さんにも伝播し、使用用途を想像しながら、真剣な眼差しで手にする姿勢が印象的でした。うつわは毎日の暮らしに潤いをもたらしてくれるもので、豊かな日々を過ごす上で欠かせないもの。作品の良さはもちろん、その奥に潜む背景を知ることで、より使う喜びは増す気がしています。展示中に手にした銀彩カップで珈琲を飲みながら改めて思うのでした。
聞き手・文 : 小野 義明
 陶芸家 福村龍太 展
陶芸家 福村龍太 展
日程 2021年2月20日(土)ー2月28日(日)
※期間中休みなし
時間 13:00-18:00